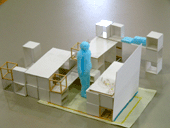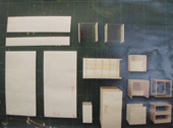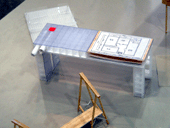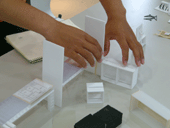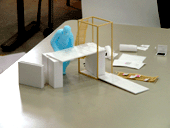|
| Design StudioⅠa | 関東学院大学工学部建築学科・デザインスタジオ1a11.APR-11.JUL 3rd year (mon)12:50-17:40 「実習棟Ⅱ」2階、203室デザインスタジオ | |
| 5th week | 05/05/09 | デザインワーク(2):機能、形体、素材、構造、寸法、ジョイント、制作方法など検討。デザインを決定 |
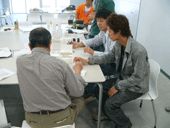 | 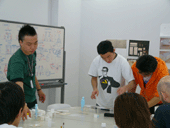 |  |  |
|
■5/09:記録 [前半]グループワーク;機能、形体、素材、構造、寸法、ジョイント、制作方法など検討。 [後半]プレゼンテーション;ワーキングシェルフおよびワーキングスペースの提案とデザインスタジオのレイアウトイメージの提案。 |
|
● Seki 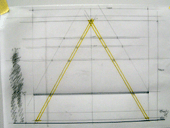 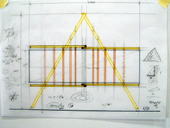 ・脚立式シェルフ。サイズは、2400w×1000d×2400h(正三角形) ・デスク、棚板裏のフックによりキャタツの開きを固定。(重力の利用) →高い所に手が届きにくいところが難点。 |
|
● Hikosaka 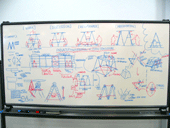 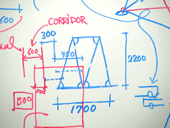 ・脚立式シェルフ。1500×1350×2200hをモジュールにして列状配置。 ・work,discussion,rest/storage,presentationなど用途に合わせて、table,variousplates,meshplatesを配置、構成する。 ・「集中する=こもる」ことではない。私物は壁面のボックスに収納し、スタジオに置かない。 |
|
● Shiraishi 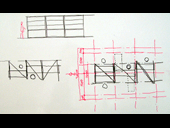 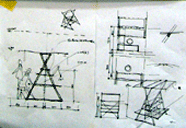 ・強度、構成材の数量など合理性を考慮して、前回見開き型から90度回転した脚立型に変更。(←取り止め) ・V型フレームからN型フレーム(1500×1500×1800)にリデザイン。 →中心部のフレームの強度、要検討。 |
| ■次週5/16の授業予定 |
|
デザインワーク(3):機能、形体、素材、構造、寸法、ジョイント、制作方法などを検討。デザインを決定。 プレゼに必要なアイテム。 1)1/10スケールの模型。人体も作ること。 2)1/10スケールの図面。平面図、断面図、立面図、システム図(要素と組み合わせの説明図)。 A3横、1枚に1アイテム。 3)60のユニットを、DS内にレイアウトした時の表現。1/20模型、図面にて表現。 各ユニットは、簡単なヴォリューム模型で表現。 4)15:00までワーク。15:30からプレゼン(10分+10分)。 インストラクターは12:50よりDLまたはDSにいます。 以上。 |
 Design Studio 1a, Department of Architecture, College of Engineering, Kanto Gakuin University in Yokohama Japan. |