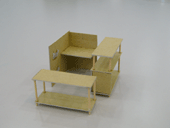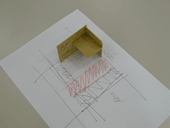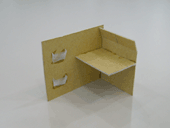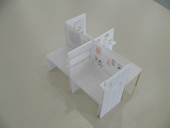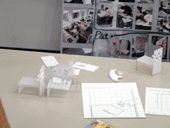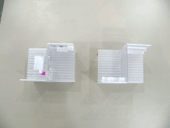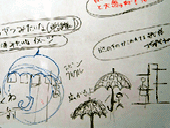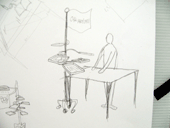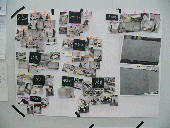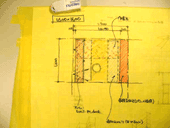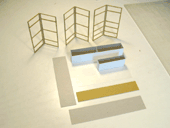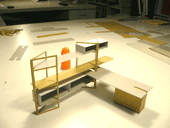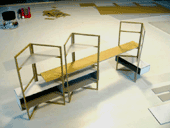|
| Design StudioⅠa | 関東学院大学工学部建築学科・デザインスタジオ1a11.APR-11.JUL 3rd year (mon)12:50-17:40 「実習棟Ⅱ」2階、203室デザインスタジオ | |
| 4th week | 05/05/02 | プレゼンテーション(2):デザインの方向性を決定 |
 |  |  |  |
|
5/02:記録 ■授業内容 ・各グループごとにプレゼンテーション(2)を行う。 ・ワーキングシェルフおよびワーキングスペースの提案とデザインスタジオのレイアウトイメージの提案。 |
|
■次週5/9の授業予定 <デザインワーク(2):機能、形体、素材、構造、寸法、ジョイント、制作方法などを検討。デザインを決定。 > プレゼに必要なアイテム。 1)1/10スケールの模型。人体も作ること。 2)1/10スケールの図面。平面図、断面図、立面図、システム図(要素と組み合わせの説明図)。 A3横、1枚に1アイテム。 3)60のユニットを、DS内にレイアウトした時の表現。1/20模型にて表現。 各ユニットは、簡単なヴォリューム模型で表現。 4)15:00までワーク。15:30からプレゼン(10分+10分)。 スタジオの大きさは、10m×18m → 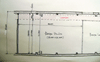
以上。 |
 Design Studio 1a, Department of Architecture, College of Engineering, Kanto Gakuin University in Yokohama Japan. |