 |
| Design StudioⅠa | 関東学院大学工学部建築学科・デザインスタジオ1a11.APR-11.JUL 3rd year (mon)12:50-17:40 「実習棟Ⅱ」2階、203室デザインスタジオ | |
| 2nd week | 05/04/18 | リサーチワーク:資料と関連情報を収集、整理、分類 |
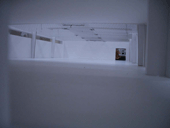 | 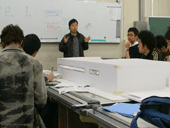 | 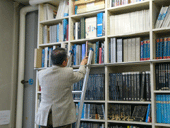 | 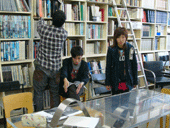 |
| 4/18:記録 |
| ■前回の宿題の確認。 |
|
1)デザインスタジオの内部模型(1/20)について。 ・スタジオとラウンジの境界であるスライディングウォールの位置を明確にする。 2)リサーチした資料について。 ・装置ばかりでなく、ワーキングスペース、デザインスタジオについてのリサーチも行うこと。 |
| ■グループ分け |
| ■用語の区別 |
|
・今回の課題において、以下の用語を明確に区別して使用します。 「ワーキングシェルフ」:デスクなどの装置 「ワーキングスペース」:装置により形成される個人空間 「デザインスタジオ」:上記を包括する空間全体 |
| ■資料収集作業について |
|
1)なんのために資料を集めるのか? ・情報を何も得ずに漠然とデザイン始めることはできない。 ・資料収集を通して、ワーキングスペースに関する基本的な構成要素を理解する。 ・現在のスタジオの動向やトレンドを知り、提案構築に活用する。 2)活用するにはどのようにしたらよいか。 ・収集した事例について、 ・それぞれなにが「テーマ」なのか、 ・どんな問題意識を持ってデザインされているのか を掘り下げて考察する。 ・多様なデザインボキャブラリーを知り、自分たちのデザイン作業へ展開する。 ・「情報の共有化」を積極的に図る→資料を「溜め込む」ことが目的ではなく 情報を再編集、再創造して「発信」、「公開」する。 3)リサーチのポイント ・オフィスや事務所のワーキングスペースの具体的な事例の収集や家具、建築についての資料収集。 ・「ワーキングシェルフ」という「装置」について(素材、可動性、寸法、構造など)。 ・なお、デザインのコンセプトを構築した段階で、再度そのテーマに沿った資料収集や編集を並行して行う。 ・収集した資料は、Web にアップする、スタジオにピンナップするなど、クラス全体で共有できるように表現する。 |
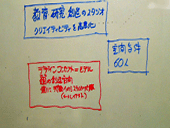
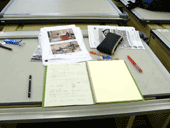

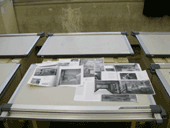
| ■「ワーキングシェルフ」に求められる機能とは。 |
|
・「ワーキングシェルフ」は、個人の創造空間・環境を構成する装置である。 ・その他の「装置」と組み合わされて「ブース」などの「個人空間」を形成する。 ・個々の「ワーキングシェルフ」や「ブース」には、相互の間で、「共働」作用を発生させるシステムが 内蔵されていることが望ましい。 |
| ■デザインスタジオに求められる空間とは。 |
|
・「ワーキングシェルフ」などの諸装置によって形成される「デザインスタジオ」とは、 大学の建築学科という教育、研究、創造のための空間・環境であり、 「クリエイティビティの高度化」をサポートする空間・環境である。 ・たとえば、「自分の部屋」も個人の創造空間となりうるが、 「デザインスタジオ」は、個と共同が、並存、共存する場所であり、単に自宅の個室が集合した場所ではない。 60人分のワーキングスペースが集まって「デザインスタジオ」を形成することの意味を十分に認識すること。 |
| ■次週4/25の授業予定(プレゼンテーション1) |
|
場所:実習棟2F 「デザインラウンジ」 1)各グループごとに「ワーキングシェルフ」についてのリサーチワークの結果発表をする。 2)一人当たりに配分されるべき「ワーキングスペース」の適正な量(面積あるいは容積)。 ①リサーチを踏まえて、備品をリストアップし、かつ数量や大きさを見積もる。 ②「ワーキングシェルフ」の大きさを誘導する。 以下は設計与件である。 ・60の「ワーキングスペース」が「デザインスタジオ」に収まること。 3)「ワーキングシェルフ」案の発表とクリティック ・デザインコンセプトが明確に形体に表現されていること。 ・模型。1案以上。(scale:1/20 表現は自由) ・「ワーキングシェルフ」をレイアウトした「デザインスタジオ」のイメージスケッチ。 以上。 |
 Design Studio 1a, Department of Architecture, College of Engineering, Kanto Gakuin University in Yokohama Japan. |