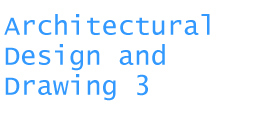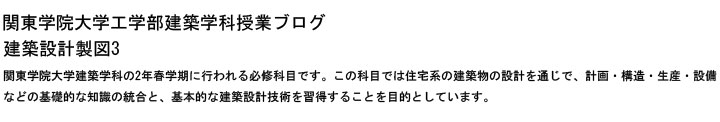課題1:「普通の家」=木造2階建て(一部でも可)、独立住宅。現在の自分の家族が一緒に住む家。敷地は、配布資料参照。4/8~6/3:8週間。
課題2:「20年後の自分の家」=RC3階建て以上。20年後の自分が、自分の家族と一緒に住む家。敷地は、比較的過密な都市的な環境。後日指定する。6/10~7/22:7週間。
なお、「課題1」の評価が不可の場合は、「課題2」には進まず、「課題1」の再制作を「課題2」とする。
これらの課題では、1)立地する場所、周辺環境と建築物の関係。2)適正な平面計画と断面計画(ゾーニングと動線)。3)適正な構造計画。4)建物の用途を充足するための空間や装置(設備計画)。5)建物の外観デザイン。以上の5項目に留意して設計案を作成すること。
「課題1」の設計条件と提出物:
1) 敷地:配布敷地図(1/2500、1/500、1/200)の図示された範囲。敷地面積:約285㎡(19m×15m)。
2)延べ床面積:120〜150㎡。建築面積:100㎡以下。建築物の最高高さ10m。
3)必要諸室(空間)と規模:各自が算定し決定する。
4)構造規模:木造2階建て(1部でも可)。
5)建物の周辺の外部空間もデザインすること。
6)最終提出物:図面(設計図書)および模型:
・A2サイズ用紙(横使い)。枚数は任意。各シート右下に、図面番号、図面名称、縮尺、氏名、学籍番号を必ず記入する。
・ 必要図面の種類と縮尺と数量:配置図(1/100、敷地周辺も表現。建物は屋根伏図で表現)、平面図各階(1/50)、立面図4面(1/50)、断面図2面(1/50)、外観透視図1点(周辺の様子も必ず表す)、内観透視図1点。エスキス(スケッチ)、ダイヤグラム(説明図式)なども添付。
・ 図面構成は自由。ただし図面の種類ごとにシートを分ける。見やすくて分かりやすく、かつ美しくレイアウトする。
・ すべての図面は手描き。提出図は原図。彩色、陰影、床や壁他のテクスチャ、点景などをきちんと表現する。エスキス(スケッチ)の用紙にはトレーシングペーパー(A3等)を使用する。
・ 表紙:設計案のタイトル、設計案の説明、模型写真、氏名、学籍番号を、表紙シートに記載する。
・ 模型:敷地全体を含む外観模型(1/50)。模型写真を表紙に添付する。
7)「課題1」作品の提出日時と場所:
2011年6月3日(金)、13時、EF館402設計製図室。
「課題1」スケジュール
第1回目04/08:科目ガイダンス。担当者の紹介。授業の目的と内容の説明。「課題1」の説明。
15時〜16時半「構造系セミナー」聴講。スタジオワーク(SW)01「自室のスケッチ」。宿題(HW)01「自室の実測図作成」。
第2回目04/15:個別指導01。SW02「配置計画と平面計画」。HW02「自分の家族が住んでいる家の実測図作成」。
第3回目04/22:個別指導02。SW03「平面計画と断面計画」。HW03「自分の家族の時間と空間」。
第4回目05/06:中間提出01。「全体イメージ模型と平面図、断面図、立面図:1/100」。個別指導03。SW04「構造計画と設備計画」。HW04「参考事例の調査と分析01」。
第5回目05/13:個別指導04。SW05「全体の再検討と1/50でのスタディ」。HW05「参考事例の調査と分析02」。
第6回目05/20:個別指導05。SW06「図面の製図と模型制作」。HW06「参考事例の調査と分析03」。
第7回目05/27:中間提出02。個別指導06。
第8回目06/03:「課題1」作品提出。採点、講評。優秀作品の発表。



2011年度「建築設計製図3」(旧「建築設計1」)課題1説明
2011年度「建築設計製図3」 シラバス
関東学院大学工学部建築学科
ARCHITECTURAL DESIGN AND DRAWING Ⅲ is a compulsory subject conducted in the second grade of the Architectural Course of Kanto Gakuin University in Yokohama ,Japan.
科目名
「建築設計製図 Ⅲ」 “Architectural Design and Drawing Ⅲ”
必修科目
キャンパス・配当年次・学期・講時・単位
金沢八景キャンパス
配当年次:2年
配当期:春学期
講時:金曜日(3講時~5講時)
単位:2
担当者
教授:関和明 Professor Kazuaki SEKI / Architectural Historian, Architect [webサイト]
大塚雅之 Professor Masayuki OTSUKA / Facilities Engineer [webサイト]
講師:木内達夫 Lector Tatsuo KIUCHI / Structural Engineer
小川守之 Lector Moriyuki OGAWA / Architect [webサイト]
小形徹 Lector Toru OGATA / Architect [webサイト]
白石越郎 Lector Etsuro SHIRAISHI / Architect
助手:森住藍 Assistant Professor Ai MORIZUMI
TA :冨澤翔 Kakeru TOMISAWA
授業の到達目標及びテーマ
この科目の目的は、設計課題の制作を通じて建築設計と製図の基本的・応用的な事項を習得することである。また、この科目は「設計・製図」分野の必修科目として、特に以下の4項目について、十全に理解することを到達目標とする。
1)設計の前提事項である、敷地特性の把握と設計条件(プログラム)の創造的な解釈を設計に活かすこと。
2)建物の機能、形体、素材、周辺環境との関係を適正に配慮すること。
3)構造および設備等の技術的な側面の解決について充分に考慮すること。
4)設計内容を設計図書ほか(図面、模型、その他)の表現手段によって十全にプレゼンテーションすること。
提出された作品は、以上の4つの観点から総合的に評価される。
授業の概要
この科目では、住宅系の建築物の設計を通じて、計画・構造・生産・設備等の基礎的な知識の統合と、基本的な建築設計技術の習得を図る。
教科書
日本建築学会編『コンパクト建築設計資料集成』(丸善)。
建築教育研究会編『住宅をデザインする:はじめての建築学―建築デザイン基礎編』(鹿島出版会)。

参考書
授業中に随時指示する。
成績評価方法・基準
課題に対する提出物の評価:100%。
関連科目
「建築設計製図I」、「建築設計製図II」、「建築設計製図IV」
履修上の注意(学生への指示)
毎回の授業に、各自の設計案を示すスケッチとスタディ模型を提示すること。また個人指導中にも、設計案のスタディを進めること。