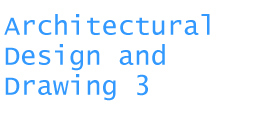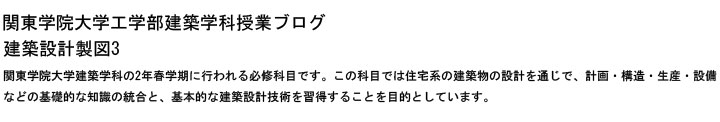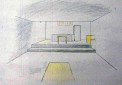自分の友達がジャズバーで演奏していれば、上階の自分の家に聞こえてくるし、降りてセッションもできる。またジャズ研の拠り所として学生も集まり活動すれば自然とOBとの繋がりもできるということでタイトルを「つながる家」とした。また、ジャズバーでの演奏がどの場所からも聞くことができるようにスキップフロアで壁の無い計画をした。住宅部分は外部階段より2階からアプローチし、2階にバスルームなど水廻りがあり、3階にキッチン、ダイニングとジャズバーの見えるリビングを配置、4階を介して5階の夫婦寝室と子供室がそれぞれスキップフロアで配置している。敷地Aを選んだ理由は、Bは住宅街で音の問題もあり、海の前で演奏できたら気持ちよいと考えたため。道路(北)側には、生活の雰囲気を隠すようにルーバーを配し、海(南)側は海を背景に演奏することを考えた。(参考:前回の模型提出+レビュー)
・道路側と海側のそれぞれの異なる特徴を持つ敷地において、どのようなことをやろうとしているのかよくわかる案で、またジャズバーの音が家全体に響き渡ることをイメージしていることも魅力あり、こうしたことが断面図で表現されているのがよくわかる。吹抜けの空間を介してジャズの音楽と暮らしの楽しさが混ざり合うことを意図した図面表現になっており、計画として結実していることに好感が持てる。計画したことをどのように実現したらよいのか、頭で思い描いたことをどのように建築にしたらよいのかを一生懸命に導き出した案で良いと思う。
・図面が弱い。線が薄くて読みづらいのが残念。
・+αの用途において、案に家に付け足し程度の案が多い中、この案は、まずのジャズと演奏する友人がいて、その考えが建物全体の計画に行き渡っている魅力ある案で、形にも反映されている。図面を頑張って欲しい。
・この建物の構造はヴォイドラーメン構造になるが、この構造の形式を上手に利用して、スラブからスラブまで開口いっぱいに取ることができるなど構造の特性を十分に生かした良い案。
・コントラストの無い図面表現で残念。紙が薄いからではないだろうか。
・これだけの大きなガラス面を設けた場合、普通のサッシでは構造的にもたないので、ガラスを支えるためのトラスなどが必要である。
・模型写真が上手に取れているが、バーの賑わいなどが表現されていないのが残念。
・ジャズが演奏されるシチュエーションを大事にして、それらを言葉ではなくて模型写真やパースなどのイメージとして表現した方が伝わりやすく良い。
・図面の描き方は、壁を塗ったり、インキングするなどちょっとしたテクニカルな手法を知れば、比較的容易にわかりやすい図面が描けるようになるので工夫して欲しい。
・各階平面図も床にテクチュアを入れるなどすると何処が吹抜けでスキップしたフロアなのか違いがわかりやすくなる。